ブロ活をしていると、しばしば“上から目線“の発言やら、あたかも“自分の知っていることだけが正しい“と言わんばかりの断定的な物言いをする人に遭遇する。
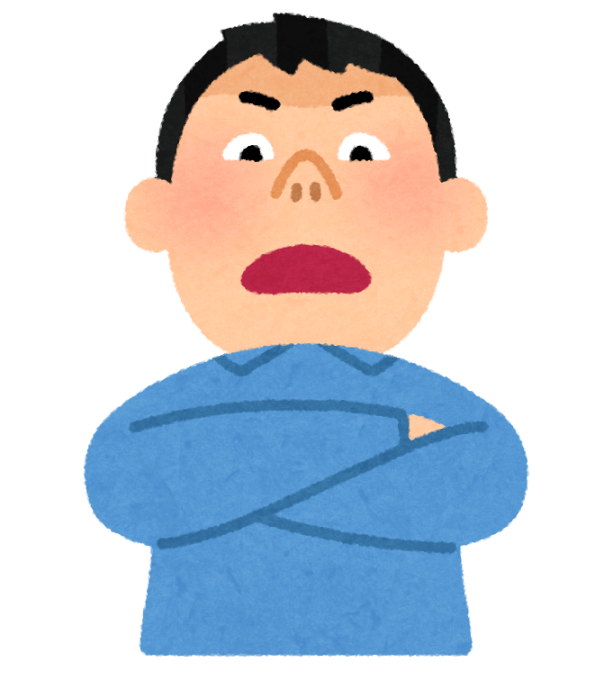
そんな時いつも思うのが、
「なぜあの人はあんなに“偉そう“なんだろう」
ということだ。
“偉そう“という不快感の背景には、往々にして“偉くないのに“という思いが付き纏う。もしこれが本当に“偉い人“(客観的に見て優れている人)が不遜な態度をとったとしても、それは“偉そう“という感想にはならず、“やっぱりオーラが違うよなぁ“などといった感想になるはずだ。
つまりわたしたちが、“偉そう“だと思うその人は、おしなべて“偉くない“のだ。
さらに別な見方をすると、その人は、「偉くないから、偉そうにしている」とも言える。
真っ当な実力を持ち、等身大の自信を持っている人であれば、自分を身の丈以上に見せる必要もないし、逆に必要以上に自分を卑下することもない。心になんらかの不安を抱えているからこそ、“偉そう“なふるまいに出るのだ。
なので、端的に言ってしまうと、「なぜあの人はあんなに“偉そう“なんだろう」という問いの答えは、「偉くないから」ということになってしまう(笑)
しかしそれだけだと、今ひとつピンと来ないという方もいらっしゃると思うので、“偉そうな態度“の対極にある“謙虚さ“について、自分の経験を元に考えてみたい。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」は、「稲穂が実るほど頭を垂れるように、学問や徳行が深まるにつれて、人は謙虚になる」という意味の諺だが、そう言った人たちの共通項として、「常に学ぼうとする姿勢」の有無があると思っている。
昔、わたしが夫と結婚した時に挨拶に行った義母方の叔父様。わたしのようなハタチそこそこの小娘の話にもちゃんと耳を傾け、「姉(義母)は世間知らずなところがあると思いますが、どうぞよろしくお願いします」と温かい言葉をかけてくださった。それだけではなく、わたしの出身大学を聞かれて答えると、「〇〇はとても素晴らしい大学ですよね」と言ってくださった。
というのも、その方T大法学部から某銀行の重役にまでなったお方なのだが、その時、聴講生として、母校の大学院で建築を学んでいて、わたしの母校の工学部の建築学科の評判を聞いていたらしい。ということで、T大を卒業して某銀行の重役にまで登り詰めた超エリートにもかかわらず、それに甘んじることなくなにかを学ぼうとする姿勢に身の引き締まる思いがしたものだ。そういう人は、常に学ぶ材料を見つけようとして、自分を変化させ、成長させようとしている。それが謙虚さの正体なのかなとわたしは思っている。
とまあ、そんなことを踏まえて、再び“偉そう“にふるまう人の話に戻ることにする。
そういった人の多くは、何事も、「これはこうだ」と決めつけて掛かる傾向がある。そうでなければ断定的に物事を語ることができず、“偉そう“にふるまうことすら出来ない。“偉そう“にしている時点でもう、自分を成長させようとか変えようとかという気持ちなど更々無い。だとすればその人は、ずっと“偉そう“なままで、決して“偉い人“にはなれないんだろうなと思ってしまう(^^)
ということで、自ら学んで成長する気概もない“偉そう“な人たちとは出来るだけ距離を置くことが、自らの成長を促すことにも繋がるのかなと思う今日この頃である。
さてさて、庭の作物についてひとつ。
これなんだかお分かりになりますか?実はこれ、去年の春先から育て、一旦収穫を終えて冬越ししたパプリカの苗なのだ。
もちろん冬の間は落葉していて、普通なら撤去してしまうところなのだろうが、とても太い幹が残っていたのでダメ元で冬越しを試みたもの。

勿論一旦鉢から出して、土を入れ替え施肥などしてみたが、水遣りする以外は基本的に放置していたにも関わらずいつのまにか実を結んでいた。
教科書通りの育て方なら、当然冬越しする前に撤去した筈であるが、なんとなく、この子の生まれ変わりたいという意気込みに応えてあげたいと思った結果である。
何事も諦めたらそれで終わり。
歳を重ねても、学び成長したいという気持ちを持ち続けていけたらと、この冬越しパプリカに背中を押されたような気がした。



コメント