それぞれの“好き“を尊重すること

白州蒸溜所ものづくりツアーに参加するにあたって、わたしはふとこんな2人のやり取りが頭に浮かんできた。
〇〇
◇◇家は大人だよね〜私はビールか甘い酎ハイじゃないと飲まないもんなあ。日本酒とかウイスキーキツイじゃん??
◇◇ > 〇〇さん
日本酒も美味しいのを飲むと気に入りますよ、きっと♪ウイスキーはね、私は要らないかな(* ´艸`)
ウィスキーや日本酒が苦手な〇〇さんに、◇◇さん「日本酒も美味しいのを飲むと気に入りますよ」とアドバイスしてるのに、自らは「ウィスキーはね、私は要らないかな(* ´艸`)」という矛盾した発言をしている。
この人の中では、日本酒>ウィスキーなのはよく分かるが、第三者的視点に立つと、これは、日本酒だろうがウィスキーだろうが、「美味しいのを飲むと気に入りますよ」と同様のことが言えるのではないかと。でも更に突き詰めると、誰かにとって美味しいものが、必ずしも別の誰かにとって美味しいとは限らない。だから、無理強いしないのはもちろんのこと、それぞれの“好き“を尊重すればいいんじゃないかな。
ところで、わたしはお酒全般が好き♪今回の白州(ウィスキー)に限らず、日本酒、泡盛、ワイン、ビール、テキーラ、ラム、なんでもござれ。わざわざ修行してJALの上級会員になったのも、“ラウンジでビールやソフトドリンクが飲み放題“だから。国際線ラウンジなら更に、フリーフードで、ワインやハイボールもセルフで思いのままだ(^^)
ただわたしは、酒好きには酒好きなりの“縛り“を自分に課していて、家では飲まない、空きっ腹では飲まない、記憶が無くなったり、吐いて気持ち悪くなるほど飲まない…つまり酒に呑まれるような飲み方はしないと決めている。
これは食事にも繋がることだが、自分にとって美味しく飲んだり食べたり出来る範囲内で飲食するということを心掛けている。それは“価値観の違い“を超えて、この社会で生きていく上で守られるべき“モラルの範疇“だと思っている。
だって嫌じゃないですか…飲みすぎて変に絡んでくる人や、トイレに篭って出てこない人とか、電車の車内や、駅のホームで何がしかを見かけてしまったりとか、いわゆる“下の話“なんて誰も聞きたくないでしょ。いくら十人十色と言ってもモノには限度がある。
ってことで、ちょっと前置きが長くなったが、今回は◇◇さんが要らんと仰る…“ウィスキーづくりの現場“を見学してきた(^^)
サントリー白州蒸溜所ものづくりツアーまで
ビジターセンターでは、予約確認・受付を行いネックストラップを貰う。

ネックストラップは「成人済み・飲酒可」「成人済み・飲酒不可(ドライバー)」「未成年・飲酒不可」で色分けされていて、飲酒可の人にしかツアー内で酒類の提供はされず、売店での購入済確認にも使われる。
ビジターセンターを抜けると売店やら見学エリアまで結構な道のりがあって、バードブリッジを渡ると…

野鳥が集まる池と様々な木々、草花が愉しめる野鳥の聖域・バードサンクチュアリが目の前に広がってくる。
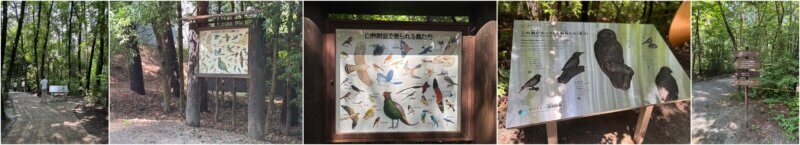
サントリーは白州蒸溜所を開設する際、野鳥が安心してすめる場所として蒸溜所の敷地を森にしたバードサンクチュアリを開園した。
蒸溜所見学のあと、天然水の工場見学に行って知ったことだが、サントリー天然水、ラベルの鳥が微妙に違っているのだ。

南アルプス(真ん中)は「ルリビタキ」、阿蘇(左)と奥大山(右)は、「オオルリ」という鳥が描かれているのだとか。
野鳥は「環境のバロメーター」と言われるほど、環境変化に敏感で、ちょっとした変化で姿を消してしまうという。そのため、多様な野鳥がすめる場所は、自然が豊かであることの証でもあるといわれている。

白州蒸溜所でのウイスキーづくりは、この豊かな自然環境の中で育まれているということを知るだけでも感慨深いものがある。
きっとこの白州蒸溜所ものづくりツアーに参加しなければ、野鳥とウィスキーづくりにも繋がりがあることなど知ることもなかっただろう。逆にいえば、何かを最初から否定してしまうことは、新たな気づきの道が閉ざされてしまうことにも繋がりかねないのだ。
ごめんなさい。いろいろなコトひとつひとつに関心がありすぎて、まだツアーまで辿りつかないわ(^_^;)
で、ここがツアーの集合場所・ウィスキー博物館だ。
今回のツアーでは、この博物館についての詳しい説明はなかったが、ここでは、シングルモルトウィスキー「白州」の歩みや、蒸溜所とその環境について多くの貴重な史料と共に紹介されている。併せて、日本や世界のウィスキーの歴史、ウィスキー文化についての展示もあり、南アルプスの山々を見渡せる展望台と共に観覧されてみては如何だろうか。

つぶやき
前後編で終わらせるつもりが、話があらぬ方向にいってしまって、疲れてしまったので本日はこの辺で。実はこの三連休、ニアをお預かりすることになっていて、なんとなく忙しい(^_^;)
関東地方は18日に梅雨明けしたそうだが、わたしの住む地域は、多少風が強いと感じるくらいで台風の影響もほとんど感じられないまま、今更梅雨明けといわれても何の実感も感じられないくらい暑い日々が続いている。とにかく朝晩の水遣りが大変すぎて、他に何もやる気が起きない(笑)
でもね、これは自分で自分を褒めていいと思うのだが、庭の草花や野菜たちはとっても元気なので有り難いことだと思っている。
みんな食べることにしか興味がないと思うが、今朝のわが家のきゅうりの花はとても綺麗に咲いていた。

あまり知られていないが、きゅうりの花は、黄色く可憐な見た目から、料理の彩りや飾りとして使われることがある。特に料亭などでは、季節感や素材の風味を生かした盛り付けに、きゅうりの花が活用されることがある。
真ん中の画像は、勝手に発芽して、いつのまにか受粉していたメロンなので品種は不明(笑)
そして向かって右側の画像は、今朝の収穫。きゅうりやししとう、ハーブティーにするレモンバーム、品種不明のミニトマト、そして中華食材として人気の空芯菜…中華料理店に行くと、空芯菜って意外と高いので驚くことがあるのだが、家庭で作ると、もう雑草レベルで飽きるぐらい生えてくる。今朝は採らなかったが、大葉もこぼれ種で勝手に生えてくるので、毎日消費に追われている(笑)
あ、そうそうなんだかあの人がブログで呟いていた。
ガイドさんに連れられ城壁を出て石段や石畳の坂道を下り旧市街へ。
やっぱりこういう市民の生活の場が楽しいなぁ。
木造建築で地震の多い日本だと大昔の町が保存されているところは少ないけれど、ヨーロッパは石材建築で地震も少ないから中世が残るね。出かける前からチェックして、自由時間には絶対買い食いしようと思ったトルデルニーク屋さんがあちこちにある。
ああ、早く自由時間にならないかなぁと思いつつ、町のガイドを受けるのであった。
あの〜プラハの旧市街は、ほとんどが観光客向けのお店ばかりなんで、“市民の生活の場“とは言えないと思うわ。たとえば京都なんか、どこもかしこも観光客だらけで、その界隈に住む方々はほぼ一般市民でないのと同じ。

それと、この方お城と教会には興味がないと仰っているけど、ヨーロッパにおける、城や教会を象徴とする歴史的建造物は、その土地に住む市民たちの“誇り“でもある。おそらく日本人が、富士山を誇りに思うことと同じくらいにだ。
そして特定の宗教を持たない日本人には理解出来ないかもしれないが、キリスト教というひとつの宗教も、その宗教観を理解することなく、市民の暮らしを真に理解することは不可能なぐらい切っても切り離せないものである。
この人ごみが、観光都市であるプラハの日常そのものであって、一見の観光客如きが、そう易々と市民の暮らしなど知る由もないのだ。





コメント